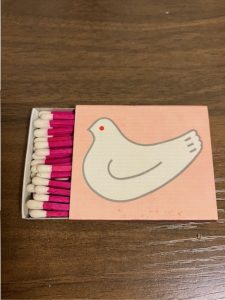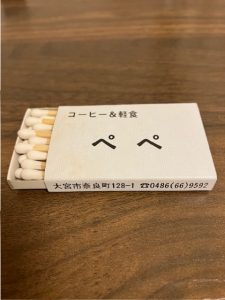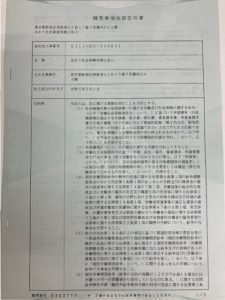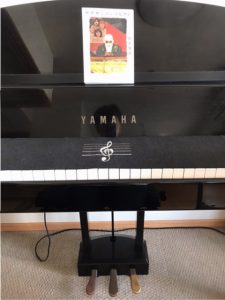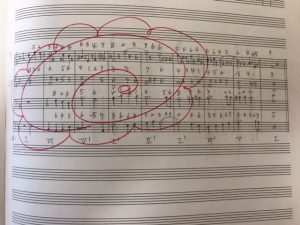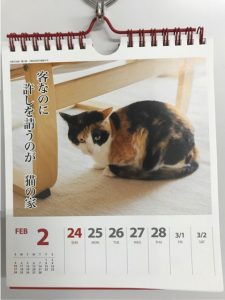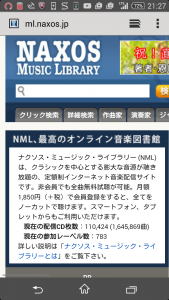みなさん
こんにちは
渡辺です。
最近、ポイ活という言葉を目にすることが多くなりました。
だいたい紹介されるポイ活の説明は
買い物やサービスを利用した際にポイントをもらい
そのポイントをPAYPAYやVポイント(昔のTポイント)等の現金と同じように使えるものに等価交換して得をする、というようなものです。
しかしどうもそれは私の知っているポイ活ではないのです。
というかPAYPAYとかVポイントに交換する、そんなものは昔からあるのでなんでいまさらという気がします。
私の知っているポイ活(というか陸マイラー)はポイントサイトであるモッピーやハピタスでクレジットカードを発行しまくって貯めた
モッピーポイントやハピタスポイント10万円分をいくつかのポイントサイトを経由してLINEポイントに等価で交換し、
LINEポイント10万をソラチカカードのメトロポイントに9万円分に交換
さらにそのメトロポイントを81000ANAマイルに交換することです。(通称ソラチカルート)
※ちなみにソラチカルートは2019年に廃止されその後LINEルート、ドットマネーTOKYUルートもなくなり、
今は一般的には永久不滅みずほルートと九州や函館で使えるルートが残っているはずですが、そのうちなくなる気もします
永久不滅みずほルートに乗せない場合はVポイントから50%でANAマイルに交換します
なお、永久不滅みずほルートはみずほ銀行の口座が必要なのでちょっと面倒な上に交換率は70%なので私はやっていません
で、それとは別に、もしくは貯めたANAマイルをANAスカイコインに交換して
羽田と那覇空港を休みの日に往復して(多いときは2往復)それを1年の間に17回くらい行い
ANAプレミアムポイントを50000ポイント貯めて(たしか羽田ー那覇間の往復でだいたい3000プレミアムポイントくらいもらえます)
(たぶん)一生有効なANAの上級会員であるスーパーフライヤーズのGOLDステータスを手に入れ
(スカイコインに交換した場合は再びを貯めた)ANAマイルを
ANAのマイルと交換できる特典航空券のサイトに交換開始日の開始時間と同時に
羽田ハワイ往復ビジネスクラス65000マイル(当時。今はもっと高いです)と交換して
(ちなみにANAの一般会員だと交換開始日や開始時間が上級会員よりも遅いので人気の日付は取れない。そして特典航空券のビジネスクラスは開放枠が少ないので人気ではない日付も家族分は取りづらい)
さらに、ANAマイルに変更するのと同時進行で世界的ホテルチェーンであるマリオットボンヴァイとAMEXが発行する
Marriott Bonvoyアメリカンエクスプレスカードを作って(同じようなカードでヒルトンカードもあります。当時はマリオットの方がホテル数が多かったのともう一つの理由でだいたいマリオットがおすすめされていました。もう一つの理由とは、マリオットに紹介で入ると紹介した側にホテル1泊分くらいのマリオットポイントが入ること。なので陸マイラーブログではヒルトンは相手にされていませんでした)
マリオットポイント貯めて(余裕があればマリオットのホテルに20連泊とかして上級会員になる)
マリオットボンヴァイが運営するハワイのラグジュアリーホテルへの無料宿泊券と交換し
羽田ハワイ往復ビジネスクラスとハワイのラグジュアリーホテルの宿泊
現金で支払うと高い時期だと往復ビジネスクラスが70万円くらいでホテルが30万円くらい合計100万円は超える旅行を元手をあまりかけずに
(ただし膨大な時間がかかり、家に大量のクレジットカードが残ります)行う
なお、マリオットの上級会員になると無料宿泊券でもスイートルームへの無料アップグレードやホテルの上級会員用ラウンジが使用できたりします
これが私の知っているポイ活です
つまりポイントを等価ではなく価値を2~3倍もしくはもっともっと高く交換することです
※スーパーフライヤーズの上級会員を取るためにANAの飛行機に乗りまくることをANA修行
マリオットの上級会員になるためにマリオットに20連泊とかすることをマリオット修行といいます
なお、マリオット修行はマリオット系ホテルは基本的に宿泊費が高額なので金がかかるため
私の頃はマリオットでも安いシェラトン函館に予約を20連泊入れて函館に行き、
チェックインだけして家に帰り、実際は泊まらないで20日後にチェックアウトだけに函館に行く人もいたそうです
ちなみに私もハワイにビジネスクラスで行くために上記を行っていたのですが20万ANAマイルが貯まったところでコロナが流行して
旅行自体ができなくなりました
さらに子供がコロナ流行初期の頃に生まれたのでより難しくなりました
基本的に3年で有効期限を迎えるANAマイルはコロナの間はANA側が期限延長を繰り返していましたが、
その期限延長も2024年3月で終わりになり
私はANAマイルの延命のためにANAスカイコインに1.7倍で交換し
そのANAスカイコインの有効期限ギリギリの2025年3月に石垣島に行ってきました

私がポイ活をはじめたのが2017年か2018年くらいなので
7年とか8年の時間を使って
けっきょくハワイには行けなかったけど石垣島もそしてポイ活自体もとても楽しかったです
ちなみに石垣島旅行は交換価値は1.7倍で良くないのですが
小さい子供がいると飛行機に乗る際
優先的に席に案内されたり
席を家族で固めてくれたりするので
まるでANAの上級会員のようでした
座席はエコノミーですが・・・
ポイ活のメリットはいろいろありますが
ポイ活をしてクレジットカードを20枚くらい発行したので
クレジットカードに多少詳しくなり
おかげでスーパーのレジなどで
他人の財布に入っているクレジットカードを見ると
その人の人生がすけて見えるようになった気がします